機構設計について
- 三次元や二次元図面を描くときの心得を知りたい。
- 設計の際に役に立つ情報を知りたい。
- どういう知識を持てば効率的に設計ができるかを知りたい。
機構設計をする際の心得ってなんだろう?
設計時に知っておくべき情報ってなんだろう?って考えたことはありませんか?
そんな機構設計者の方にお伝えしたいことを、現役8年目の機構設計者が自分の経験談(特に失敗談・・・)をもとに記事にしましたので、参考にしていただけると幸いです。
三次元図面を書くときの心得
三次元図面を書くとき、私は下記を心得として考えてます。
これらは手を抜くとよく痛い目にあいましたので、面倒な点もありますが、きちんとしたほうがいいと考えるようになりました。
内部から描く
例えば基板の入るケースであれば基板から
何かを動く装置であれば、その可動部からといった具合です。
設計上、外形サイズが決まっていたりと制約が多いこともありますが、
私の場合、内部はあとで、、、と放置してみると、結局どうしようもなくなってやり直すことが多ので、内部をきちんと決めてから、外側に入っていきます。
図は干渉させない
当たり前でしょ!?って思うかもしれませんが、最近検図をしていると、干渉している図を書いてくる人が出てきましたので、あえて書きました。
「後で加工図の公差で指示するからいいです」という言い訳をされますが、いろんな部品があると加工図だけではつじつまが合わなくなりますし、出来上がったもので不具合が生じると、どこがおかしかったのかわからなくなってしまいます。
また、他の人が三次元図面を見たときにも意図が伝わりませんし、いろんな人にその言い訳をすることが効率がいいのかと疑問に思います。
もの同士を接触させるような図を書く際は、もの同士がめりこんだ図面にならないように、もの同士を篏合させる場合には、きちんと篏合時のクリアランスを設けるようにしないとダメだと思います。
篏合に関しては、加工精度の公差も考えてクリアランスを設けることが大事です。最悪の場合、はまらなくなります。
寸法は小数点1桁までにする
ミクロン単位の図面を書く場合は別ですが、寸法が少数点1桁以下にならないようにしたほうがいいと考えます。
例えば10.56㎜など、少数点2桁以上がでてくると、見難い図面になります。
また、加工図に展開するときも、きれいな寸法にならないため、間違えやすい図面になり、トラブルのもとになります。
存在するものは描く
基板の実装部品やら、ネジやら、よく面倒くさがって描かない人がいますが、描くように心がけしたほうがいいと考えます。
私も、面倒になって描かないことがありましたが、そういったときに限って、他の部品がぶつかっていたりとミスを起こしていたので、極力描くようにしてます。
よくあるトラブルが、基板の配線経路がないとか、ネジの先端同士がぶつかって組み込めないというものです。
こういった単純なミスが排除できるように細かい部分まで描くように心がけています。
加工図面(二次元図面)を描くときの心得
加工図面って誰がみるのか?。それは加工屋さんである第三者ですよね。
しかも三次元と違って細かい部分まで見られますし、適当な図面を描くとその人のモラルが疑われると思うんです。
そういった第三者への配慮を忘れずに図面を描くことが大事だと思います。
二次元図面を描くとき、私は下記を心得として考えてます。
正面図は適当にしない
図面を加工図に落とし込む際に一番最初に考えるのは、正面図をどこにするかだと思います。
この際、できる限り隠れ線で表現しない方向にしたほうがいいと考えてます。
複雑な図面になるほど、隠れ線は加工屋さんにとっても間違いのもとになると思います。
基本は三面図(正面図、平面図、右側面図)にすることですが、必要な場合は左側面図、下面図、背面図、断面図、矢視図を準備しましょう。
また、加工方法によっても図面の向きは変わります。
例えば旋盤であればチャックが左側にあり、バイト(切削工具)が右側にありますよね?。
なので、それを考えてあげて正面図で掴むほうを左側にもっていきます。
両側加工するのであれば加工の多いほうを右側にもっていきます。
フライスであれば上からエンドミル(切削工具)で加工しますよね?
なので、それを考えてあげて正面図の下側に加工品の底面をもっていきます。
寸法の基準を意識する
基準とは寸法の書き出す際のスタート地点のことを言ってます。
基準を設けることでわかりやすい図面になりますし、例えば、正面図に対し左下を基準するというルールをもっておけば、書き出し時点で悩みませんし、慣れてくるとスラスラ描けるようになっくると思います。
いろんなルールはあると思いますが、実際、わかりやすい図面が優先だと思います。
また、正面図でできる限り寸法をとって、ごちゃごちゃしている図面より、正面図では外形寸法や見難くならない程度で一部の寸法を記載し、他の面の図で寸法をとってあげるなどの配慮をしたほうがわかりやすい図面になると思います。
意匠面、仕上げの記載をする
意匠面の記載をして、キズ等に気を使ってほしい場合とか、仕上げの記載をして、精密加工をしてほしい場合とか、配慮してもらいたい場合があります。
逆に仕上げを緩く指示すればもっと簡易的な加工で済むとか
費用対効果も出てきます。
いずれにせよ指示をせずに、すりキズだらけの部品が来て、トラブルにならないためにも記載は必要と思います。
設計の際に役立つ情報
ここでは、基本的なことを記載してますが、これらを把握していないと設計時に意外と悩むものですし、よりベストな設計ができないと思います。
また、最近検図をしていると無駄に溶接構造であったり、いかにも強度不足な図面に出くわすことがあったのであえて記載いたしました。
加工材料の特性を知る
加工材料の特性を知っておけば、どの材料を使うか設計時に悩んだ際の選定基準になると思います。
材料には、鉄、ステンレス、アルミ、樹脂・・・等々、たくさんあります。
鉄の中でもSPCC、SECC・・・、ステンレスの中でもSUS304、SUS430・・・、等々、いろいろあります。
強度を求めるならば、鉄やステンレス、アルミといった金属を使用しますね。
その中でもコスト重視なら鉄、錆を気にするならステンレス、軽量化するならアルミといった選択肢になると思います。
なかなか、経験側的な話で、正解を出すのが難しい場面も出てきますが、どういった場合に、どの材料を使うべきか日々整理していったほうがよいです。
難しくて悩んで進まないという人は、とりあえず、コスト重視というポリシーで大型物件には鉄のメッキ品、もしくは鉄の塗装品で検討し、中型や小型の物件には、ステンレスやアルミといった考え方でもいいかもしれません。
中型や小型物件になってくると、人の目に留まりやすいために、錆や軽量化が求められ、ステンレスやアルミを使うことが多くなります。
加工方法を知る
素材ごとで加工方法も変わってきます。
例えば、金属ものの加工方法で言っても、プレス、レーザー、フライス、旋盤、成型・・・いろいろありますね。
数百個から製作するものは、プレスやレーザー、成型で作れるように考えないといけないですし、少量製作といった場合には、フライス、旋盤でもいいかと思います。
加工方法を知ることで、できる形のイメージが沸くので、より安く、早く設計する能力が身に付くと思います。
やはり、加工方法を知らないと溶接じゃないとできないような図面になってしまい時間と費用が掛かってしまいます。
でも加工方法って細分化すると、まだまだたくさんありますので、少しずつ知っていけばいいと思います。
その加工方法が必要なったときに、きちんとメリット、デメリットを確認していくことが大事だと思います。
また、加工屋さんもできることが日々進化していますので、その都度確認することも大事だと思います。
加工限界を知る
加工方法を知る際に、加工限界も知ったほうがよいと思います。
例えば、板金加工については、最小曲げ寸法、曲げニガシ寸法、端面からの穴位置寸法などなど、いろいろあります。
私もたまにありますが、加工限界を確認せずに設計して、いざ手配時にできませんと言われやり直す・・・といったミスを起こします。
なので、加工限界を知ることで、設計のやり直し等のリスクを回避できます。
こちらも最初にたくさん勉強するのではなく、必要になったときにきちんと確認・整理するという心積もりで取り組んでいくことが大切だと思います。
あと、わからないことは、恥ずかしがったり、手間と思わずに、加工屋さんに聞いたほうが早いです。
もっとよいやり方を教えてもらったり、チェックポイントやら含んだ一覧表を頂けるケースもありますので、調べるよりも格段と早いペースで学ぶことが出来ると思います。
市販品を知る
一から設計・製作しなくても、市販の部品で安く手に入る場合があります。
なので市販の部品をリサーチしておいたほうがいいと思います。
あとから、市販品があったことに気づいて後悔することは多いです。
市販品を調査する場合は、有名な総合商社で下記があります。
・misumi
・RSコンポ―ネンツ
・Digi-key
・チップワンストップ
これらはメカニカル部品も数多く提供しており、ときには三次元図面も提供していますので、設計の助けになります。
どういう部品があるか知っているだけでも、あなたの強みになりますよ。
また、これらの商社では素材の特性やら、設計の計算方法等の技術資料もたくさんありますので、とても勉強になると思います。
やはり、一から設計するより、市販品で売っているものを流用したほうが、早く安く済みます。
特に切削や成型が必要な部品を一から作るよりもあるものを流用できるのであれば、大きな費用効果を生み出すでしょう。
まとめ
ここでは、機構設計の時に役立つ情報と題して、私の三次元図面、二次元図面を描くときの心得や、材料の特性、加工方法、加工限界について書きました。
私自身がミスして、次は気を付けようと思ったこともありますので、ぜひ参考にしてもらえると幸いです。
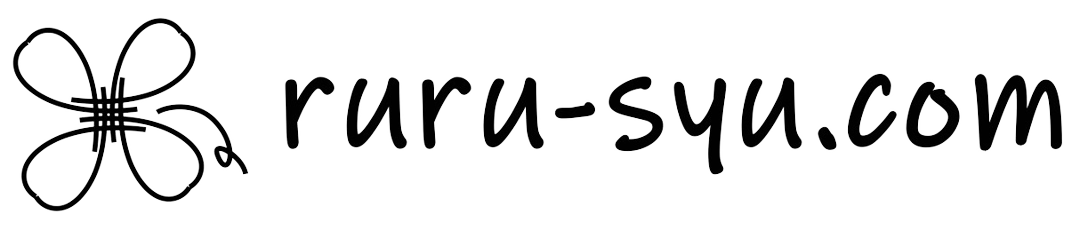







コメント